今回は、どうやってASDの診断を勝ち得たか?の記録です。
夫の言動に、ずっと「なぜ?」という違和感を抱えながら生活していました。
でもそれが何なのか、私にはずっとわからなかった——。
そんな日々が続く中で、ある出来事をきっかけに、夫がASD(自閉スペクトラム症)かもしれないという疑いが芽生えました。
今回は、そこから実際に診断を受けるまでの「病院探し」と「診断確定までのリアルな道のり」を書いてみたいと思います。
🧩第1章:気づきのきっかけ
きっかけは、夫がサウナ中に倒れて救急搬送されたことでした。
その3日後に長男が高熱を出し、のちに肺炎と診断されました。
家族に迷惑をかけているのに、夫は一切謝ることもなく、救急搬送と長男の肺炎の関係について「因果関係を証明しろ」と言ってきたのです。
その瞬間、「この人、普通の感覚ではない」と本気で思いました。
心が限界を迎えた私は、自分が壊れそうだと思い、診療内科を受診。
医師との会話の中で、「あなたは“カサンドラ症候群”かもしれませんね」と言われ、「カサンドラって何ですか?」と尋ねたことが、すべての始まりでした。
心が限界を迎えた私は、自分が壊れそうだと思い、診療内科を受診。
医師との会話の中で、「あなたは“カサンドラ症候群”かもしれませんね」と言われ、「カサンドラって何ですか?」と尋ねたことが、すべての始まりでした。
▼夫への違和感を初めて意識し始めた頃のエピソードはこちら
👉 カサンドラかもしれないと疑い始めた私の記録
🏥第2章:病院探しの壁
私が通っていた診療内科では、「大人の発達障害を診てくれるクリニックは限られていて、ここからは直接紹介できないので、自分で探してみてください」と言われました。
そこで初めて、大人のASDを診察してくれる病院が、子どものそれに比べて圧倒的に少ないという現実をネット検索で知ることになります。
1件目の病院では「新規は受け付けていません」と断られ、2件目では「大学生までしか診ません」と言われました。
さらに3件ほど電話をかけましたが、どれも「毎月決まった日時に、ネットで先着2名だけ新規受付」という方式。
働きながらその時間にPC前にスタンバイするのは現実的に無理だと感じ、心が折れそうになりました。
それでもエリアを少し広げて探し続けた結果、開院して半年も経っていない新しいクリニックを見つけました。
ネット予約が可能で、「ここしかない」と思い予約しましたが、最短でも予約日は1ヶ月先でした。
それでも「ようやくたどり着けた」と、ほっとしたのを覚えています。
🧠第3章:診察とASDの診断
クリニックのサイトには、「初診時に準備しておくとよいもの」のリストが記載されていました。
具体的には、幼少期の通知表や、当時の養育者(親など)からの証言があると診断に役立つとのことでした。
一番望ましいのは「ご両親のどちらかに同席してもらうこと」でしたが、夫の両親は地方に住んでおり、来てもらうことは難しく、義母がA4用紙2枚にまとめた幼少期の記録を送ってくれました。
また私は、これまで日常で「おかしい?」「どうして?」と感じてきた夫の言動を、ブログに書いてきたような形で整理し、エピソードをまとめたメモを初診日に医師へ提出しました。
初診当日は約60分ほどの時間が確保され、問診票の記入後、夫への聞き取りが始まりました。
子どもの頃の様子、学校や職場での人間関係、家庭内でのトラブルやこだわりなど、かなり具体的な質問が投げかけられました。
私も同席し、家庭での困りごとを丁寧に伝える機会をいただきました。
診察の最後に、医師からは「ご主人、一度心理検査を受けてみられますか?」と提案がありました。
この検査には90〜120分程度かかり、自費診療で、結果が出るまでに約1ヶ月かかるという説明がありました。
夫はそれを了承し、初診の1週間後に心理検査を受け、そしてその1ヶ月後、3回目の受診で診断結果が出る流れとなりました。
診察の日、医師は心理テストの結果を見せながら丁寧に解説し、「ご主人はASDといっていいでしょう」と診断を伝えました。
私はその瞬間、「やっぱり!私は間違ってなかった」と心の中でガッツポーズをしていました。
涙が出そうでした。自分を責め続けていた年月が一気にほどけるような感覚でした。
しかし、その安堵も束の間、夫が豹変しました。
普段はおとなしい夫が、「なんでこんな結果になるんですか?」「何を根拠にそんなことを言うんですか?」と医師に詰め寄ったのです。
医師が「このような基準書に基づき、総合的に判断しています」と冷静に説明しても、「こんなええ加減な診察は到底受け入れられない」と言い放ちました。
私は診断書を出してもらいたかったのですが、夫が診断を受け入れず、診断書の発行を拒否されてしまいました。
私はASDの証明として診断書を持っておきたかったのに、それすら叶わず、とても悲しい気持ちになりました。
💭第4章:診断を受けて感じたこと
「やっぱりそうだったんだ」という納得と、「これからどうすればいいの?」という不安が入り混じっていました。
でも、ASDという言葉が与えられたことで、私の中でようやく“原因”に形がついたのは確かでした。
診断を受けた瞬間、私は「自分は間違っていなかった」と確信し、ふっと心が軽くなったのを覚えています。
涙が出そうでした。でも、その安堵も長くは続きませんでした。
夫は診断をまったく受け入れず、帰宅後も夫の両親に電話で「こんな診断は信じられない」「受け入れられない」と話していました。
今も、夫自身も、義両親も、ASDの診断を認めていません。
それを自分の診療内科の医師に伝えると、「セカンドオピニオンで別の病院でもう一度検査を受けてみては」と言われました。
もし2か所で同じ結果が出れば、夫もさすがに納得するのではと。
でも、私は思いました。
再び病院を探して受診させるのは、正直もうしんどい。
1回目は「自分はASDではない」と信じていたからこそ受診に応じた夫も、2回目は拒否する可能性が高い。
だから私は、1回でも診断が出たことで、もう十分だと感じました。
私の中では、それで納得ができたのです。
まとめ:わかることで、前に進める
夫の診断をきっかけに、私たちの関係が劇的に変わったわけではありません。
でも、ずっと抱えていたモヤモヤに“名前”がついたことで、私は少しだけ前を向けるようになりました。
診断のことを両親に話すと、「よく頑張ったね。本人が納得していなくても、あなたの中で一つの区切りがついたなら、それでよかったんじゃない?」と言ってくれました。
その言葉に、私は救われた気がしました。
書籍などでは「ASDのパートナーには具体的にやってほしいことを細かく伝える」といったアドバイスが紹介されています。
でも、私はそこまで関係改善を望んでいるわけではありません。だから、そのようなアドバイスは今の私には響きません。
たとえば先日、家計簿をしめるために「今月のレシートを出して」と伝えたら、本当にレシートだけを出してきた夫。
ネット代やAmazonで買ったものもあるはずなのに、と思って「全部出してと言ってるのに」と言うと、
「レシートを出してって言ったやん」と。
以前なら「いや、わかるでしょ!」とイライラしていたところですが、今は違います。
「ああ、出た出たASDの典型例」と、少し余裕を持って対応できるようになりました。
ASDの夫を持って苦しんでいるのは、あなただけではありません。
モヤモヤしているなら、一度、配偶者に受診をお願いしてみるのも一つの方法かもしれません。
診断がすべてを解決してくれるわけではありませんが、「原因が見えること」で、自分自身が少しラクになるかもしれません。
これは、私自身がようやく踏み出せた「心の記録」です。
同じように悩んでいるあなたに、少しでも届きますように。
診断がすべてを解決してくれるわけではありませんが、「原因が見えること」で、自分自身が少しラクになるかもしれません。
※以下はPR広告を含みます。
誰にも話せずに一人で悩んでいる方へ。
ASDのパートナーとの関係や、自分の気持ちの整理について、誰かに聞いてほしいと感じたことはありませんか?
国内最大級のオンラインカウンセリングサービス【Kimochi】 なら、スマホやPCから匿名で気軽に専門家に相談できます。
「相談すること」に少しでも心が動いたら、ひとつの選択肢として検討してみてください。
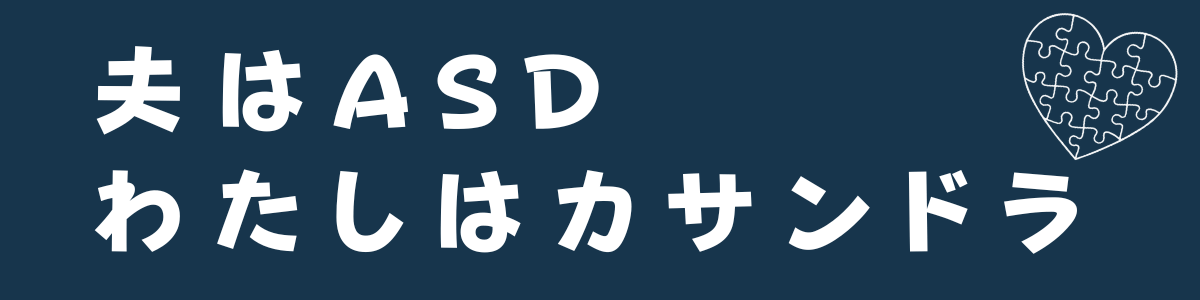

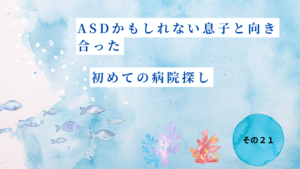
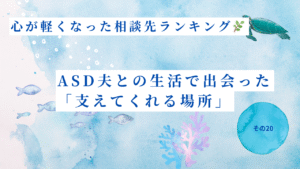
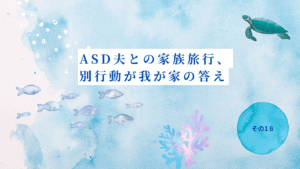
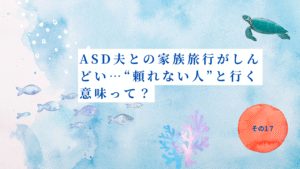
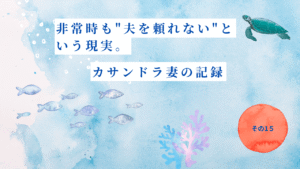
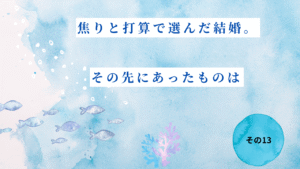
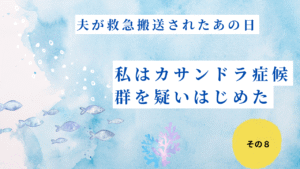
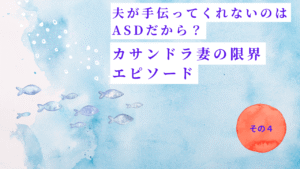
コメント