今回は、本当に困っている子どもの小児科通院のお話です。
子どもが熱を出したとき、あなたの家ではどうされていますか?
わが家では、私が仕事の都合で行けないときは、ASD夫が小児科や耳鼻科に連れて行きます。
一見ありがたい話なのですが、正直なところ私はとても不安です。
なぜなら、夫はASD(自閉スペクトラム症)の診断があり、病院での「説明」や「報告」がまったくできないからです。
💬 エピソード:伝わらない、わからない、任せられない
毎日一緒にいる子どもなので、
- いつから
- どんな症状が
- どれくらい
これくらいのことであれば、夫が医師に直接説明できる、というかしなければいけないと思っているので、お願いしているのですが、
お医者さんになんて言えばいいかわからない?紙に書いて
とお願いしてきます。こちらも忙しいので、これとこれがいついつからと口頭でいうと、理解できない。紙に書かないと病院に連れて行かないと言い出します・・・。
そして、診察が終わり、帰ってきた時
診察結果どうだった?
と聞くと、風邪。薬はこの薬の袋に書いてあるとおり。
とだけ言って、自室に引きこもります。それが一回ではなく、毎回です。想像できますか?一般の理解ある夫ならこんなことにはなりません。
さらに困ったことに、私はいつも家を出るのが早いので朝の薬は飲ませてほしいのですが、
なんで薬を子どもに飲ませないのか?聞いたところ、
薬を飲むのではなく自然治癒力で治すべきだ。治したいなら、自分で薬を飲むべきと小1、小3の子どもに言ってます。
小学校低学年の子供が容量、用法守って自分ひとりで薬飲めますか?
と、ASDに聞いてますが、知ったこっちゃないという返答が帰ってきます。
🧠 ASDの特性と夫の行動のつながり
このような夫の言動に、はじめは「なんでそんなこともできないの?」とイライラしていました。
でも、ASDについて本やネットで調べるうちに、夫の行動には特性が関係していることがわかってきました。
ASDの人に見られる特性(夫の場合):
・言語的なやりとりが苦手:口頭で状況を説明したり、医師の話を要約して伝えることが難しい
・予測できない事態に不安を感じる:病院という環境自体がストレス
・自分のやり方へのこだわりが強い:「薬を飲まなくてもいい」と一度思うと、それを変えにくい
・他人の期待や不安を想像しづらい:私が報告を待っていることに気づかない
🌱 いま、私が工夫していること
こうした夫の特性を理解してからは、少しずつ私も対応を変えるようにしています。
- 症状のメモは、完結に箇条書きで
- 受付に電話して「夫はASDです」と一言伝えておき、後から電話で説明をお願いすることもある
- 薬については、小さなお皿に錠剤を出して、付箋をつけて朝ゴハンのあとに飲むと貼って子どもに直接飲むように伝えてます。
それでもうまくいかないこともあります。
でも、「理解されないイライラ」ではなく「仕組みを作っていく」という視点を持つことで、気持ちが少しだけ楽になりました。
🕊️ 締めくくり:同じように悩んでいるあなたへ
ASDの夫と育児をしていると、「え?なんでそれができないの?」と思う場面が本当に多くて、
そのたびに一人でモヤモヤを抱えてきました。
でも、それは私が悪いわけではなく、夫との脳の特性のちがいなのだと少しずつ受け入れられるようになりました。
それでも疲れるとき、限界を感じるときはあります。
そんなときに「私も同じ」と言ってくれる誰かの言葉に、私は何度も救われました。
このブログが、誰かにとってそのひとことになれたらうれしいです。
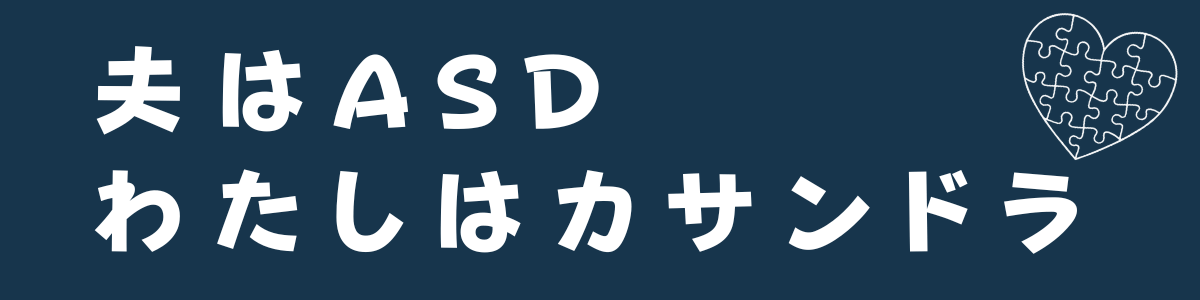

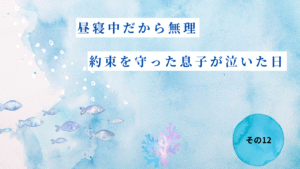
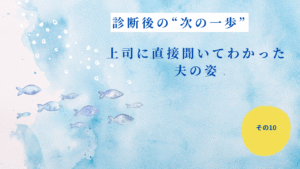
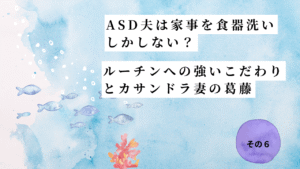
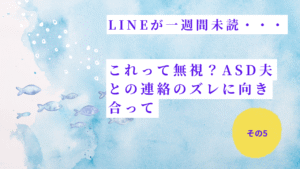

コメント